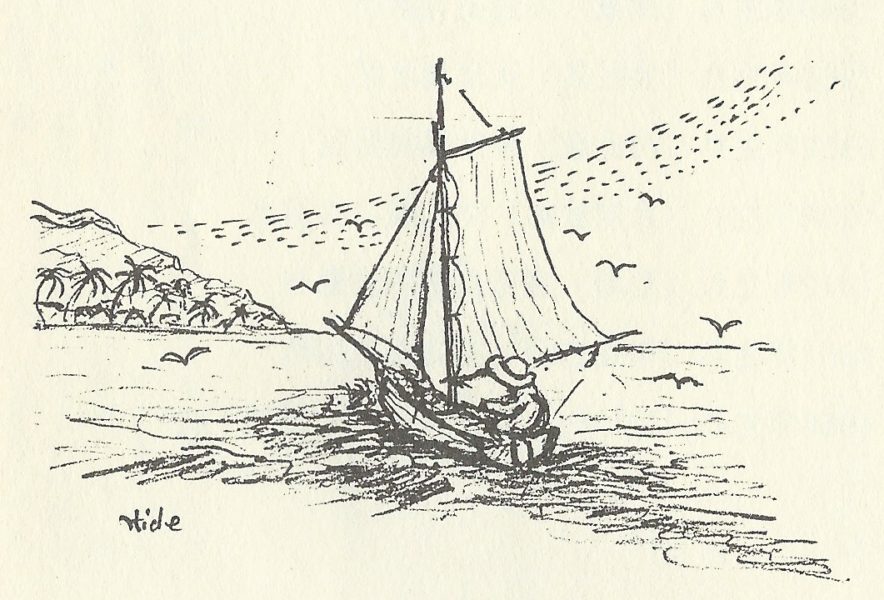私があの島へ釣りへ行ったのは今から40年以上前のことだ。
その島の名をここには書かない。なぜかと言えば、そこは仙人の住む島だからである。その島では、夜になると月の光に誘われてジャングルの中からヤシガニが這い出てきて海水に浸ると信じられていた。私はその島の人里から離れた海岸のジャングルの中で半年ほどキャンプをし、毎日魚を釣って暮らした。これはそのときの話である。
キャンプ地の前はアダンの茂みがあり、そのすぐ先は真っ白な砂浜で、珊瑚礁が途切れるあたりにエメラルドとウルトラマリンの交差する海があった。そこにはアダンの葉が風にそよぐ音と、明るい海景、遠くに轟く潮騒、泳いだ後の快い疲労とむっとした暑さのかもし出すアンニュイがあった。
昼寝から覚めてハンモックから地面に降りると、私はいつも手モリと釣りの仕掛けを持って海に入った。珊瑚礁が途切れるあたりは海中の断崖で、突然何百メートルも深くなっている。そこには巨大なテーブル珊瑚がビルのように立ち並び、その谷間のラビリンスに色とりどりに着飾った魚たちが無数に泳いでいた。青い闇のような海の底からはしばしば化け物めいたナポレオンフィッシュやサメが姿を現した。
私はしばしば珊瑚礁の間に潜り水中で魚釣りをした。竿は2メートル以下、仕掛けは小さなオモリに針だけ。餌には自家製塩引サンマの切り身を使う。泳いで魚の群れに近づき、連中の目先に餌をぶら下げてやる。
ミーバイはアブラコのようなやつで疑うということを知らず、ぱくっと餌をひと飲みする。決して釣られることのないツノマン(テングハギ・草食性?)はさも人をばかにしきったような顔をして、あの小生意気なおちょぼ口で器用に針だけを残して餌を切り取って見せる。そういう時、私はもう一方の手に持っている水中銃を一発おみまいしてやる。
ミーバイは味噌汁にすると絶品だ。ツノマンの刺身はフグよりも美味だと思う。南の魚は身がしまっていないからまずいというのは迷信だ。身のしまった魚はいくらでもいるし、美味な魚もたくさんいる。この島で一等美味な魚、それはガーラ(ロウニンアジ)だ。こいつは猛牛のように荒れ狂う。流線型の魚体は美しく、力にあふれていた。ガーラを釣る前に、私は島人から借りた投網でミジュン(イワシに似た魚)を獲った。生きたミジュンの体に大きな針をしばりつけ、ガーラのくる場所に投げるのだ。ミジュンが手に入らぬときはミジュンによく似たスプーン(ダイワ社のダンサー)を使用した。ガーラは12号の道糸を簡単に切るやつだから油断はできなかった。
私は潮を見て、ちょうど頃合になると毎日ポイントの岩場に行きガーラを狙った。一週間ほど通って一本釣ればよいという感覚でやる。これは野ゴイ釣り師の呼吸と同じだ。そうやって待って待って、ある日ガーラが食いつくと死闘がはじまる。こういうとき私は生きていることを真に実感できた。格闘の末どうしても上げられぬとき、私はモリを手に海に飛び込んでガーラにとどめを刺した。
時には最も凶暴な、1メートルもあるシージャー(ダツ)が掛かった。5インチもあるヤリのような口ばしに歯がずらりと並んだところは小型の一角怪獣だ。ガッと見開いた獰猛な眼はいまにも火を吹きそうな感じがした。こいつはときどき矢のように飛んできてダイバーの体に突き刺さり、ダイバーは大怪我をしたり死んだりしている。危険極まりないやつなので同情はいらない。私はシージャーを釣り上げたときはすかさずコン棒でぶちのめした。この魚は白身で肉はやや青みがかっているが、フライにするとなかなかうまい。
そうやって私は毎日釣りをし、釣った魚を日々の糧として暮らしていた。ある日私は島の奥へ旅し、道なき道を辿り、「仙人」と呼ばれている人間に出会った。その場所は人里から遥か遠く離れた、文明と完全に隔絶した小さな湾であった。仙人の住む小屋の裏には小川があり、澄んだ水が流れていた。小屋の横手にはイモ畑があった。小屋の手前の大きな木がつくる木陰は涼しくて魅力的だった。木と木の間には手製のハンモックが吊るされ、そのハンモックに横たわると青い海が夢のように美しく見えた。
年の頃は60を少し越え、髪も髭も白かった。しかしどう見ても仙術を使うような人間ではなく、気のいいビーチャー(酔っぱらい)の類であった。酒さえあればごきげんで、「世の中の事などどうでもいい、ダーンとやれ、ダーンと」と飲むほどに気勢を上げた。酒の肴は眼の前の海にいくらでもあった。タテ網で獲ったボラの刺身、潜って獲ったモズクや朝鮮サザエ、海岸から餌木(一種の擬餌針)を投げて獲ったイカの塩焼、青いパパイヤとイノシシの煮付け、この世の珍味が山盛りだ。
私はそれからしばしば酒を持って仙人を訪ねた。島人の中には彼の職業はドロボーだという人もいた。でも彼の小屋の中には金もなければ柔らかなフトンもなかった。すすけたナベとヤカン、粗末な夜具に手製のランプ、島の歴史を書いた本、海辺で拾ったらしいガラス玉や浮き木、そんなものしかなかった。私はしだいにこの老人の超俗性とそれを意識もせず自然に振る舞っているところが好きになった。こんなところに一人で住んでいて淋しくないかと聞くと、「なーに、うるさくなくていい。俺の仕掛けたワナにイノシシが掛かったら、俺は村に行き、酒と交換するんだ。そのときは村にしばらくいることもある」とこたえた。
今の時代の日本にこんな人間が存在すること自体まさに神話である。私がその島を離れて数年後、風のうわさでその仙人が死んだことを知った。私は彼が住んでいたあの島に再び行きたいとは思わない。主のいないあの桃源郷はもやはただの原始林に過ぎない。行っても悲しいだけだ。あの仙人は今も私の思い出の中に生きている。
マスターの冒険旅行記
釣り夜話